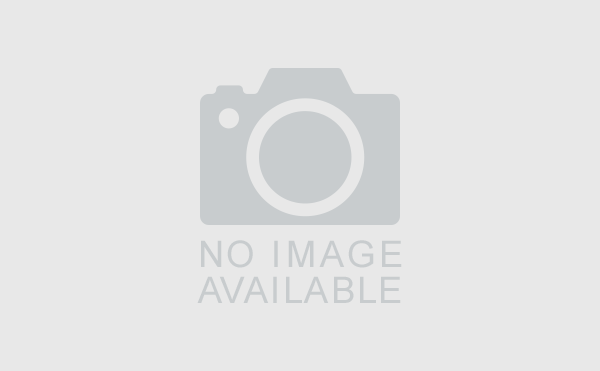会主のお話し
「心とは」その一
会主 丸山維敏
何を今更「心」とはなどと大袈裟に、とお思いでしょうが、これは紀元前から古化ギリシヤの哲学者達が考え続けてきた「人間とは何か」という、彼等にとっての一番中心的な課題だったのです。
以前、私は「氣とは何か」という題で、私の私淑する理論物理学者の保江邦夫博士の理論物理学でいうところの「素粒子」、そして「フォトン(光子)」について書かせて頂いたことがありました。
そもそも物理学とは読んで字の加く、物の理(ことわり)を解明する学問で、目に見ることの出来ない「心」とは関係のない学問、すなわち唯物論の学問なのです。
そこへ、日本で初めてノーベル物理学賞を授与された湯川秀樹博士の最後の愛弟子である保江邦夫博士が、湯川秀樹博士の「素領域理論」を更に発展をさせて「唯心論物理学」なるものを打ち立てました。
素領域というのは、それ以上分割できない空間の最少単位です。それはツブツブの泡の様はもので、湯川博士はその泡と泡の間をエネルギーが飛び移っているのが素粒子で、その泡が集ったものがこの宇宙空間である、と捉えたのです。
しかし、当時の物理学界では、冷やかに誰もこの「素領域理論」を認めようとはしなかったのです。そこで唯一の愛弟子であった保江博士は、これをスイスの大学に留学中に数学的に解明し、その論文をアメリカ物理学会とアメリカ数学会に提出し、欧米の数理物理学専門誌で発表されたことで、これを「ヤスエ方程式」とよび、世界中の物理学界から認められ有名になられたのです。
こうして、素領域理論が正しかったことが数学的に証明され、微細空間がどのような構造になっていることがわかりました。
これを知った、当時病床にあられた湯川博士は「私の素領域理論も、ここまで来たか」と満足氣に笑ってお亡くなりになったそうです。
因みに保江博士は、今でも湯川博士の命日にはお墓参りを一度たりとも欠かせたことはないそうです。
只、ここでギリシヤ哲学以来の「人間の本質とは何か?心とは何か?」という課題は残されたままでした。
これをまたもや解明したのが、保江博士とその京都大学在学中の唯一の親友である中込照明先生だったのです。
私はこれを保江邦夫博士の五十四冊のご著書を読破した者の務めとして、これから「唯心論物理学」をご紹介し、「心とは」を解明していきたいと思います。
この稿の最後に当たり、かの有名なベーブ・ルースの言葉をのせて頂きます。
「あきらめない奴に、勝てる者は居ない」
次回へ。