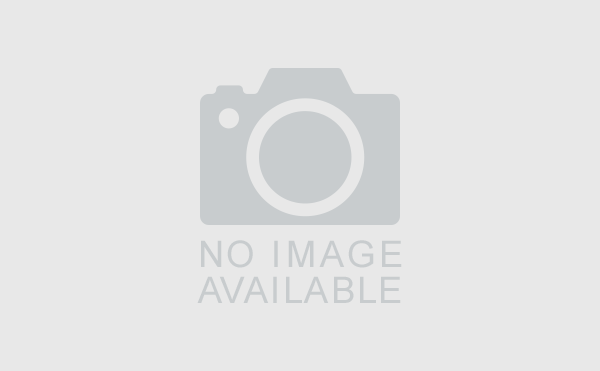会主のお話し
「心とは」その二
先号で私が私淑する保江邦夫博士の提唱する「唯心論物理学」にもとずいて「心とは」を解明すると記しました。従ってこれからの文は殆ど保江博士の御著書が参考となります。
さて、私達が生活しているこの地球が存在しているのは、誰もが認めるこの宇宙という大空間の中です。この大空間の中を動いている全ての星々の動きに着目して神が創られたこの世界を解明しようとする学問は「宇宙学」と呼ばれてきました。
この宇宙学という学問はギリシヤ時代におこりました。
ギリシヤ哲学といわれるこの学問は、その中心的な課題は「人間とは何か」「心とは何か」ということです。その為には、人間を存存せしめているこの世界や宇宙を理解しなければならない、ということから、そのような本質を追い求めたのがこの学問、すなわちギリシヤ哲学の始まりなのです。
そして多くの哲学者たちが、他の動物や植物には見られず、人間だけが持っているものは何か、と各々が思い思いに考えた挙句の結論が、それは肉体ではなくて「心」(精神、霊魂、意識)ではないかと考えました。
つまり、人間の本質である「心」と世界・宇宙についての関係を明らかにする、これが「宇宙学」の始まりなのです。
この「宇宙学」の始祖である古代ギリシヤの天文学者、プトレマイオスが唱えた天動説が、中世まで西洋での「宇宙学」の基本となりましたが、後に現われたコペルニクスが太陽を中心にした地動説を唱えたことにより、がらりと変わりました。
つまり、古代ギリシヤ人にとっての世界というのは、自分たちが住んでいたエーゲ海周辺だけだったのですが、それ以降の天文学や科学の発展などによってそのスケールが徐々に拡がっていったのです。
人類の世界や宇宙に対する眼差しは、やがて地球から太陽系へ、更に銀河系へと拡がり、現代の宇宙論では、ビックバンから始まったとされる137億年前までを含んだものになっております。しかし、現代ではここまでが限界なのです。何故かというと、ビックバンが始まって、それが地球に映像として届いたのが137億年かかった今なのです。
1光年は9兆4600億キロメートル、宇宙の拡がりは9兆4600億キロメートルの137億倍まではわかっておりますが、それ以前はどの天体望遠鏡にも未だ届いていない為わからないということです。
「人間とは何か」その本質を知りたくて、スタートした私達が住むこの空間。つまり人間は「ヒト」です。霊が止まるから霊止、つまり人なのです。でも何故「人」といわず「人間」というのでしよう。それは空間があるからです。空間は間です。間がピッタリだから「間に合う」間がずれると「間に合わない」。
相手との間がかみ合わないと「間がもたない」で「間延び」して「間(魔)がさす」から「間違える」。相手の思う間に入るから「間入りました(参りました)」。間が近くなり人間的に狭いのを「間締め(真面目)」。間が空きすぎるのを「間抜け」。つまり間とはエネルギーそのものなのです。間は大事なのです。
その空間を何処までも追っていった結果が137億年の先まで行ってしまったのです。
人類は人間の本質を知ろうというところからスタートして、世界や宇宙はどうなっているかを科学的にも探求し続けた結果、ただただ本質を理解しないまま、観測を続け、肝心要の「人間の心とは何か」という本質的な問いについての解答は得られていません。
「宇宙やこの世界は、それを人間が認識するから存在している」この考えを「人間原理」といいます。
次回はこの「人間原理」につき記します。
以上